
金星よりも内側を回る水星の場合だと、最近の日面通過は、1993年、1999年、2003年に起こっており、それほど珍しい現象ではないかもしれません。しかし金星の日面通過となると話は別です。なんと前回起こったのは1882年12月6日、日本国内で見られたのは1874年12月9日ですから、明治7年以来130年ぶりの現象です。ですから、今生きている人で金星の日面通過を見たことのある人は誰ひとりとしていません!
金星が日面通過 2004年6月8日

![]() 130年ぶりの珍現象
130年ぶりの珍現象
金星よりも内側を回る水星の場合だと、最近の日面通過は、1993年、1999年、2003年に起こっており、それほど珍しい現象ではないかもしれません。しかし金星の日面通過となると話は別です。なんと前回起こったのは1882年12月6日、日本国内で見られたのは1874年12月9日ですから、明治7年以来130年ぶりの現象です。ですから、今生きている人で金星の日面通過を見たことのある人は誰ひとりとしていません!
![]() 金星の日面通過とは
金星の日面通過とは
金星は地球の軌道の内側を回る内惑星ですから、地球から見た金星は太陽からある一定の角度以上離れることはありません。金星は太陽の付近をウロウロと動き回っている間に、偶然に太陽と同じ方向に見えて、太陽の表面上を通過していくように見える場合がありますが、これを金星の日面通過と呼んでいます。
下の絵をご覧ください。地球−金星−太陽が一直線に並んでいますね。このとき、地球から見ると金星は太陽と同じ方向に見えるはずです。金星が日面通過となる場合は必ず内合となっていることがわかります。金星と地球の会合周期(内合から内合までの期間)は583.92日ですから、金星の日面通過は約584日間隔で起こりそうに思いますが、実際にはそう単純ではありません。
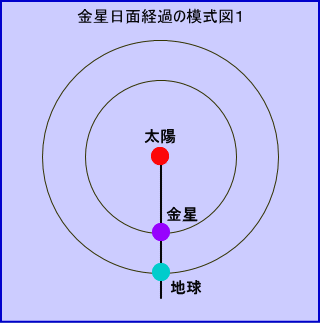
下の絵をご覧ください。地球の軌道を真横からみた場合、金星の軌道は地球の軌道に対して3.4度傾いています。このため内合であっても、金星の位置が上下するため日面通過とならない場合がほとんどです。例えば金星が(A)の位置にある内合の場合では、地球から見て金星は太陽の下側に見えることになり、日面通過とはなりません。金星が地球軌道面を横切るタイミングで内合にならないと日面通過とはならないのです。そんなわけで、金星の軌道が地球の軌道と交差する地点が太陽と同じ方向に見える位置に地球がやってくる、6月7日前後か12月9日前後にしか金星日面通過は起こりません。
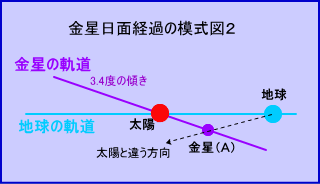
![]() 位置関係の確認
位置関係の確認
それではここで、地球、金星、太陽の位置関係を確認しておきましょう。下の絵は、ちょうど金星日面通過が起こっている頃の太陽系の様子を、「つるちゃんの3D太陽系 シェア版」で表示したものです。
太陽が原点にあり、そこから金星、地球の順に、3者が一直線に並んでおり、金星が内合となっていることがわかります。注目してほしいのは金星の位置です。軌道の色が水色の部分は地球の軌道より上側にあり、青色の部分は地球の軌道よりも下側にあることを示しているのですが、金星はちょうど水色から青色に変わる付近にいます。
つまり、金星は地球の軌道面近くにあり、なおかつ地球と太陽を結んだ直線上に金星がうまく乗っています。先も話たようにこれが少しでもずれると、地球から見た金星は太陽方向からズレてしまうので、日面通過にはなりません。今回はまさにドンピシャリなタイミングというわけです。
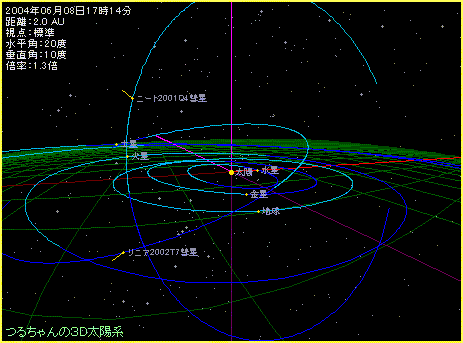
![]() 当日の経過
当日の経過
前置きはこれくらいにして、当日の日面通過の様子を見てみましょう。下の絵は太陽面を金星が通過していく様子をしめしたものです。左側は赤道座標系、右側は地平座標系(東京)によるものです。進行状況は観測地点が違ってもほとんど同じです。実際に観測する際には右側が参考になりますが、高度や方位角に違いが出てきます。
| 金星の通過の様子(赤道座標系) | 金星の通過の様子(地平座標系) |
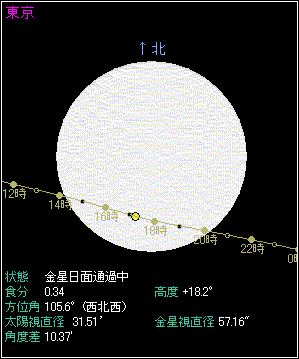 |
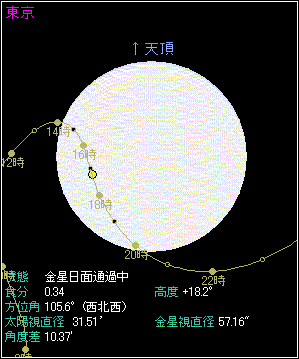 |
金星は14時11分頃から太陽面に差し掛かります。その後少しずつ太陽の内側へ入り込んでいき、17時14分頃に3分の1くらいまで入り込んで太陽の中心へ最も近づきます。その後、金星は太陽の中心から少しずつ離れていきますが、日面通過の状態のまま日没を迎えてしまうので、最後まで観測することはできません。
・「日食と月食」のアプレットを開く ・「食の種類」を金星日面通過に変更 ・前回検索ボタンを押して、今回の金星日面通過を表示 ※多少の誤差を含む点をご了承ください。 |
![]() 観測データ
観測データ
各地での観測データを掲げておきますので参考にしてください。(月刊天文2004年1月号による)
| 観測地 | 開始 | 食最大 | 金星の入り | ||
| 時刻 | 高度(度) | 時刻 | 高度(度) | ||
| 札幌 | 14時11.9分 | 51.8 | 17時14.1分 | 18.8 | 19時10分 |
| 東京 | 14時11.3分 | 55.0 | 17時13.8分 | 18.2 | 18時54分 |
| 京都 | 14時11.5分 | 58.3 | 17時13.9分 | 21.1 | 19時10分 |
| 福岡 | 14時11.7分 | 62.9 | 17時14.0分 | 25.1 | 19時25分 |
| 那覇 | 14時11.4分 | 66.6 | 17時13.9分 | 25.8 | 19時20分 |
![]() 金星の日面通過を観測しよう
金星の日面通過を観測しよう
金星日面通過の観測方法や観測にあたっての注意点をあげておきましょう。
水星の場合よりも大きいぞ
当日、金星の見かけの大きさは57.2秒もあります。これは当日の太陽の大きさの33分の1の大きさですから結構な大きさです。水星日面通過の場合と比べると、金星は水星の5倍近い大きさに見えますから、かなり迫力があると思いますよ。イメージは、先に出てきた「金星の通過の様子」の絵を参考にしてください(少し大きめの黄色の丸印)。
天体望遠鏡で観測する
いくら金星が大きく見えるといっても1分に満たない大きさなので、肉眼では金星を識別することはできません。観測するには天体望遠鏡が必要となります。天体望遠鏡で観測した金星は内合ということもあって地球へ接近しており、予想以上に大きく見えるのではないでしょうか。右の写真は水星の日面通過の例ですが、これなんかとは比べ物にならないくらい、大きな黒丸の金星が観測できるのではないかと思います。なにせ、水星の5倍近い大きさですから。
金星は黒く見える
地球から見た金星は太陽を背にしているので、影の部分しか見えません。したがって金星は小さな黒い丸型に見えます。ちょうど、日食の際に月が黒い丸型をしているのと同じことです。右の水星日面通過の写真を参考にしてください。
移動を観測しよう
金星は少しずつ太陽の表面上を動いていくように見えます。その速さはゆっくりとしたものですが、少し時間を空けて観測すると移動が確認できます。
太陽の減光をお忘れなく
当然のことですが、太陽をまともに見ると失明の危険があります。次の注意点を守って楽しく観測しましょう。
・絶対に肉眼で直接太陽を見ないようにしましょう。
・どうしても肉眼で見なければならない場合は、日食グラスを使ったり、白黒フィルムの黒くなった部分を通して見るようにします。
注)カラーフィルムは赤外線を通すので危険です。
・天体望遠鏡で観測する場合は、口径を4センチ程度にまで絞った上で、投影版などに映し出すようにします。
注)口径を絞らないと太陽の光を集め過ぎて危険です。
注)接眼レンズ部は高温になるますので十分注意しましょう。
・投影版が利用できない反射式望遠鏡などの場合は、口径を4センチ程度にまで絞った上で、接眼レンズに太陽観測用のサングラス(専用のフィルター)を着けて観測します。
注)長時間見続けるとサングラスが破損する恐れがあり非常に危険です。このことから最近ではメーカからもサングラスはほとんど販売されていません。積極的にお勧めできる方法でないことを付記しておきます。
・接眼レンズは、熱に強いタイプ(H、MHなど)を使用します。
![]() 今後の金星日面通過
今後の金星日面通過
次回の金星日面通過は2012年6月6日に起こります。この時は今回よりも条件が良く、太陽の外側から40%まで内側へ入り込みます。しかし、その次となると2117年12月11日まで待たねばなりません。といってもその頃まで長生きできる人はいないかもしれませんが。
水星の場合を含めて今世紀中に起こる日面経過は、天文用語ミニ解説の中にある東京の日面通過を参照してください。